ここは「みんなの居場所」。アシックス里山スタジアムに生まれた“ご近所さん”の温かい輪
人々が自然と触れ合い、交流する「里山」をコンセプトに、多種多様なコミュニティ活動が生まれているアシックス里山スタジアム。
その理念を象徴するのが、社会福祉法人来島会によりスタジアムに建設された「コミュニティビレッジきとなる(以下、「きとなる」)です。ここにはカフェ「里山サロン」と福祉事業所が一つ屋根の下にあり、サッカーを愛する人々だけでなく、障がいのある方や発達に特性を持つ子どもたちも集い、共に学び、働き、支え合うユニークな空間が生まれています。

※計画初期のパースのための実際の建物と一部異なります。
今回は、そんな「きとなる」で働くスタッフたちの声を取材しました。

篠原杏奈さん(来島会)
来島会が運営する「きとなる」内にある就労支援を中心に行う多機能型事業所「ジョブサポートセンターここすた(以下、「ここすた」)」のスタッフ。作業療法士。2024年よりここすたに勤務。プログラムの作成や就労アセスメント等を担当し、ご利用者様の目標実現に向けて、成長を支援している。
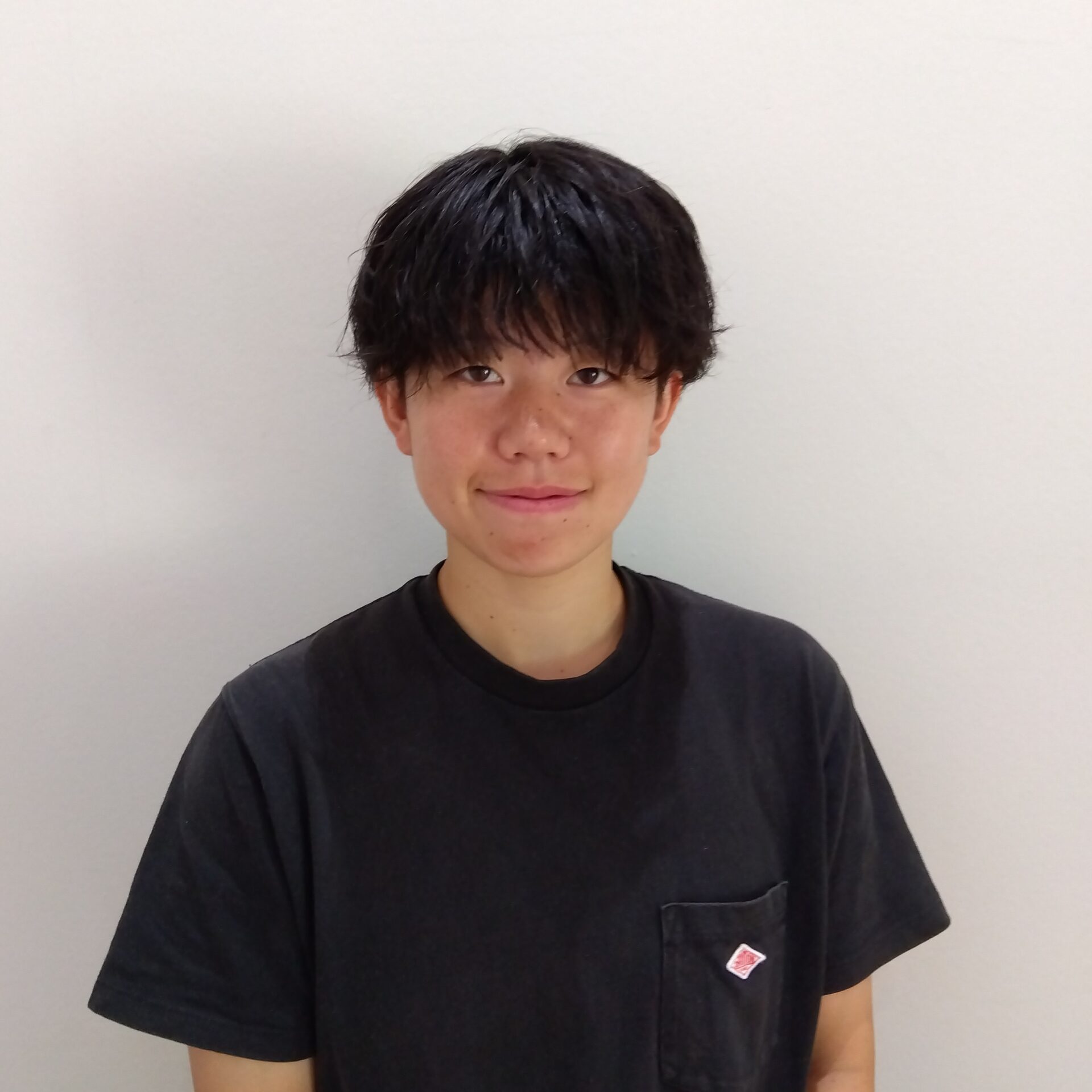
濱渦柚花さん(来島会)
来島会が運営する「きとなる」内にある放課後等デイサービス事業所「らびっつ」スタッフ。2025年4月新卒で来島会へ入職。FC今治レディースの選手として活躍するとともに、らびっつの児童指導員として子どもたちの療育に従事。感覚統合を担当し、遊びや体験を通じて子どもたちの発達をサポートしている。

飛田文子さん(FC今治)
「きとなる」内にあるFC今治が運営するカフェ「里山サロン」スタッフ。里山統括グループ所属。里山サロンのマネージャー、スタジアムの運営管理に従事。
「何か一緒に」から始まった小さな一歩
──カフェと福祉事業所というのは一見すると異色の組み合わせですが、どのような連携が生まれているのでしょうか?
飛田さん: スタジアムが完成する前から、FC今治と来島会さんには交流があり、ここ「きとなる」がオープンした当初から「何か一緒にやりたいですね」という話はしていました。でも、当時は自分たちの業務をこなすのに精一杯で…。そんな時、「隣にいる来島会さんの利用者の方に、就労訓練として何か作業をお願いできないか」というところから、連携がスタートしました。
篠原さん: 多機能事業所「ジョブサポートセンターここすた」では、障がいのある成人の方を対象に、就労に必要な訓練をしています。最初にいただいたのは、テイクアウト用の紙袋やカップに、ロゴのスタンプを押す作業でした。
飛田さん:そこから、毎週月曜日の定休日の清掃、営業中の洗濯や植木の水やりなど、少しずつ業務委託の幅を広げ、サロンの運営に欠かせないいろんなお仕事をお手伝いいただいています。
篠原さん:場所が近いからこそ、日常的に連携しやすいのがありがたいですね。ご利用者様自身が里山サロンへ直接「在庫はありますか?」と聞きに行ったり、備品を借りに行ったりする機会が増え、自発的にコミュニケーションをとる練習にもなっています。里山サロンのスタッフさんにも覚えていただき、より責任感をもって仕事に取り組んでいるように感じています。

濱渦さん: 「きとなる」には、就学期の子どもたちが通う放課後デイサービス「らびっつ」もあります。お隣同士の関係の中から、「里山サロン」を舞台にお買い物体験を実施したこともありました。
飛田さん: お金や人と関わる経験をしたいというご相談をいただいて、かき氷やスコーンの特別メニューを作りました。子どもたちが、自分で注文して「お願いします」と言っている姿はとても微笑ましかったですね。
濱渦さん: 今年は中高生が「職業訓練」としてカフェの片付けを手伝っていますが、慣れない環境での体験に試行錯誤しながら、少しずつ集中力もついてきているように感じています。普段過ごす施設の中だけでなくて、地域とつながる実践の場所が隣にあるという環境は、ご利用者様が社会の一員として成長していくための貴重な機会になっていると思います。
自然な交流が育む、温かい関わりあい
──こうした交流から、何か変化を感じますか?
飛田さん: 業務をお願いするうちに、一人ひとりの人柄を知ることができ、本当の「ご近所さん」のような関係が生まれています。お店にお客さんとしていらっしゃってくださることもあり、挨拶したり、ちょっとした世間話をしたりするような関係性になってきました。
時には利用者さんの行動を「大丈夫かな?」と心配して「きとなる」のスタッフさんに伝えたりと、互いに見守り合うような温かい関係性ができています。
篠原さん: ご利用者様にとって、里山サロンやスタジアムという環境は、とても良い社会参加の機会になっています。施設の中にいるだけだと、職員以外の大人と接する機会は少ないですから。以前は挨拶が苦手だった方が、自分から話しかけるようになるなど、良い変化を感じています。

濱渦さん: 昨冬からは、子どもたちが制作した絵を里山サロンに飾らせてもらうようになったんですが、自分の作品がいろんな人の目に触れることで、子どもたちにとっても喜びや大きな自信につながっているようです。ご家族が絵を見にサロンに立ち寄ってくれたりと、より結びつきも強くなったように感じています。
飛田さん: お客さんの反応も変わりました。店内に絵を飾るようになって、「隣にこんな施設があるんだね」と興味を持ってくれる方が増えました。これまでカフェの利用が目的だった方々も、スタジアム全体のコミュニティに関心を持つきっかけになっているようです。

スタジアム全体へ広がる「共助」の輪
──連携の舞台は「きとなる」の外にも広がっているのだとか。
飛田さん: 昨年は来島会さんが主体となって、スタジアムで畑を始められたんです。野菜がもりもり育って、来場者の方も興味を持っていたのが印象的でした。
篠原さん: 畑仕事の経験があるご利用者様をリーダーに、畑作りに挑戦したんです。収穫した野菜は調理訓練で使うだけでなく、地域食堂に寄付できるほどたくさん採れました。スタジアムのスタッフや来場者との会話のきっかけになったのはもちろん、「らびっつ」の子どもたちと「ここすた」のご利用者様が、苗の植え方や手入れの仕方など、畑作業を通じて交流する良い機会にもなりました。

篠原さん: 今年はご利用者様と地域の方が交流できる新しい方法を模索する中で、スタジアムでキャンプを企画しました。テントを立てたり、カレーを作ったり。一晩かけてじっくりと交流を深めることができ、普段はインドアなご利用者様が積極的に挑戦するなど、新たな一面を発見できたのが大きな収穫でした。
飛田さん: たくさんのテントが並ぶ様子は、里山サロンのお客様にとっても面白かったようで、「何をやっているんですか?」と興味を持ってくださる方もいました。スタジアムという開かれた場所だからこそ、こうした活動がお互いに見え、そこから新たな繋がりが生まれることを改めて実感しましたね。

一緒につくるスタジアム、ここは誰もが主役になれる場所
──今後の展望を教えてください。
飛田さん: 今以上に手を取りあいながら、この場所に一緒に賑わいを作っていきたいですね。スタジアムの芝生をみんなで育てる「芝ふみ」にも、利用者の皆さんに参加いただいています。この場所を盛り上げていく仲間として、一緒に活動できる機会を増やしていきたいです。
現在、FC今治でも来島会さんの後に続いて、「里山ファーム」という畑活動を始めました。「みんなでお世話デー」を設けて、スタッフ総出で取り組んでいますが、来島会の職員や利用者さんにも一緒に混ざっていただけたら嬉しいですね。
濱渦さん: FC今治のホームゲームがある週末には、金曜日に子どもたちがスタンドの椅子を拭いたり、清掃を手伝ったりと、試合に向けた準備にも関わっています。こうした活動を通じて、ボランティアやサポーターの方々と顔見知りになり、交流する子どもたちも増えました。「みんなで一緒にスタジアムを作っている」という実感が、子どもたちの誇りにもつながっていると感じていますね。

──今後、新たに挑戦してみたいことはありますか?
濱渦さん: 子どもたちの得意な絵や工作を活かしたアートイベントをやってみたいですね。作品をスタジアム内に展示しながら、来場者の方々と交流できる機会を作れたら、子どもたちにとっても特別な思い出になると思います。
他にも、FC今治には障がい者向けのスクールもあるので、手を取り合い、誰もが楽しめるミニサッカー大会を開催できたら面白いなと思っています。
篠原さん: 自分たちの「やったこと」が場に残る経験は、子どもたちやご利用者様にとって大きな意味を持ちます。サッカーやアートを通じて、スタジアムというたくさんの人が集まる場所で、多様な人々と出会い、自分を表現する機会が、ご利用者様の新たな趣味や生きがいにつながると期待しています。これからも施設の中だけでなく、外に出て様々な経験を積み重ねる機会を増やしていきたいです。
おわりに
今回お話を伺った「きとなる」は、サッカーを通じて地域を盛り上げるFC今治と、福祉事業を運営する来島会が、それぞれの専門性や強みを持ち寄り、自然な形で支え合う場所です。
初めは小さな「何か一緒に」から始まった活動は、少しずつその幅を広げています。
「里山サロン」のスタッフと「ここすた」の利用者さんが互いを気遣い合う姿。子どもたちが描いた絵が、訪れたお客さんの心を和ませる瞬間。スタジアムで共に汗を流しながら、ボランティアやサポーターの方と笑顔を交わす子どもたちの姿。
「きとなる」を舞台に生まれる交流は、まるで森の木々が寄り添うように、自然な形で広がっているように感じました。ここで芽生えた交流が今後どのように広がっていくのか、これからの展開が、楽しみです。
取材 / 小林友紀(企画百貨)

